健康経営
体調悪化が行動ミスに変わる瞬間
― 酷暑ストレスが“判断エラー”を引き起こす組織リスク ―
今年も全国各地で、危険なレベルの酷暑が続いています。
もはや「暑さ対策」という言葉では収まらず、酷暑ストレスは業務判断そのものを狂わせるリスク要因になっています。
ここで、はっきりさせておきたいことがあります。
事故を起こすのは「体調不良」ではありません。
体調悪化が、行動ミスに変換される“判断の瞬間”です。

発熱は最大級の「身体ストレス」である
感染症にかかると、体は意図的に体温を上げます。
これは免疫細胞を活性化し、病原体の増殖を抑えるための進化的防御反応です。
しかし同時に、発熱は
- <li”>全身代謝の亢進
- 心拍数増加
- ホルモン分泌の急変
を引き起こす、極めて強いストレス刺激でもあります。
酷暑下では、この「発熱に近い状態」なのです。
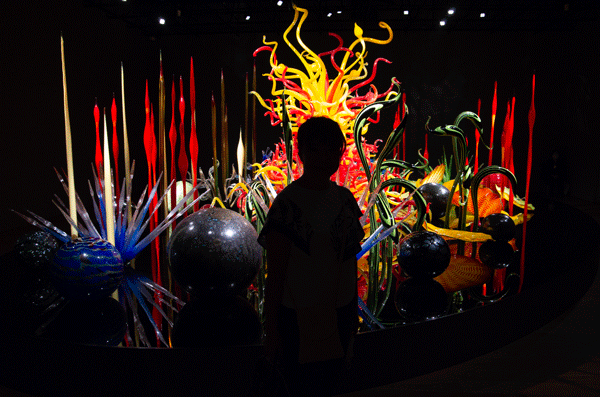
酷暑・うつ熱・熱中症と血糖値異常
高温多湿環境では、
体温調節が追いつかない
- 熱放散が阻害される
- いわゆる「うつ熱」状態になる
このとき体内では、
ストレスホルモン(コルチゾル等)が急増します。
その結果、
- 肝臓での糖新生が促進
- インスリン作用が相対的に低下
- 血糖値が急上昇
という反応が起こります。
これは肥満・高血糖傾向のある人だけの話ではありません。
誰にでも起こりうる生理反応です。

血糖値が上がると、何が起きるのか
血糖値上昇は、以下の反応を引き起こします。
- 強い眠気
- 判断スピード低下
- 注意力の狭窄
- イライラ・焦燥
重要なのはここです。
本人は「判断力が落ちている自覚」をほとんど持てません。
つまり、
-
体は限界に近い
-
でも「いつも通り」と判断してしまう
この瞬間に、
体調悪化 → 行動ミス へ変換されます。
事故は「突然」ではなく「変換点」で起きる
多くの現場事故は、
-
突然起きた
-
予測できなかった
と報告されます。
しかし実際には、
-
暑さ
-
疲労
-
血糖変動
-
判断単純化
が段階的に積み重なった末の結果です。
問題は、
「どの時点で止まるか」が、個人任せになっていること
です。
セルフケアでは、この問題は止められない
-
水分を取る
-
休憩を取る
-
ストレッチをする
これらは重要です。
しかし、
-
判断が鈍っている本人に
-
正しいセルフケア判断を委ねる
こと自体が、構造的に無理なのです。
必要なのは「共通判断軸」を作る教育
この問題を解決するには、
-
体調を良くする教育
ではなく -
判断が狂う前提で、どう止まるかを決める教育
が必要です。
具体的には、
-
どの状態を「危険」とみなすか
-
誰が止める権限を持つか
-
申告・中断が評価される設計
こうした判断の設計は、
研修という形でしか統一できません。
なぜ外部研修が必要なのか
このテーマは社内では、
-
個人の体調管理の話にされやすい
-
「自己責任」にすり替わりやすい
-
本音が出にくい
という特性があります。
外部研修だからこそ、
-
科学的事実として
-
個人攻撃にならず
-
組織リスクとして整理できる
のです。
人事・総務の皆さまへ
もし現場で、
-
暑い時期にヒヤリが増える
-
判断ミス・手戻りが増える
-
「集中力が落ちている人」が目立つ
のであれば、
それは健康問題ではなく判断設計の問題です。
けんこう総研では、
-
酷暑ストレス
-
血糖変動
-
判断低下の構造
を踏まえた 組織向け研修 を提供しています。
▶ 教育設計・研修導入のご相談はこちら
https://kenkou-souken.co.jp/contact/
ここまでお伝えしてきた内容は、
個人の自己責任ではありません。
暑熱環境下では、
「我慢する」「気づけない」「無理をしてしまう」
という行動が、誰にでも起こり得ます。
だからこそ必要なのは、
個人任せにしない「教育設計」と「判断基準の共有」です。
けんこう総研では、
暑熱ストレス・判断低下・我慢が事故につながる構造を、
労働安全衛生教育の視点から整理し、
現場で共有できる形に落とし込む支援を行っています。