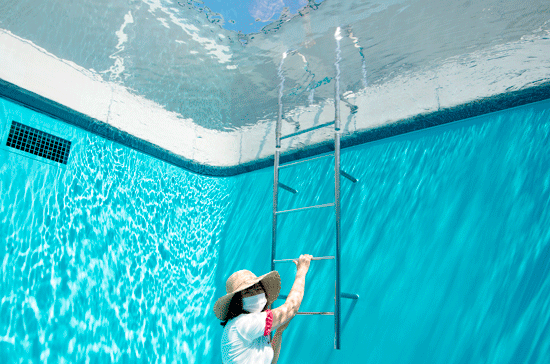おすすめ
残業ストレスでランナーズハイ?脳内麻薬エンドルフィンの正体
2025年5月15日更新
「残業で疲れているのに、妙にテンションが上がって止まらない」
そんな感覚を経験したことはありませんか?
実はこれ、脳内から分泌される“脳内麻薬”のようなホルモン、エンドルフィンやドーパミンの影響かもしれません。
本記事では、ストレスと脳内ホルモンの関係を科学的に解説しながら、職場でのメンタル不調を予防する視点を紹介します。
さらに、組織全体の働き方を見直すための「ストレス管理研修」についてもご案内します。
ストレスによる疲労と「ハイ」状態の関係
連日のように続くパソコン作業や納期のプレッシャーに追われる中で、気づけば「妙なハイテンション」になっている…。
それは単なる気合や達成感ではなく、脳内の快楽物質が放出されている状態かもしれません。
強いストレス下では、身体が“自分を守るため”にエンドルフィンやドーパミンを分泌し、一時的な快感や高揚感を生み出します。
この状態が俗に言う「ランナーズハイ」に近いメカニズムです。
脳内ホルモン「エンドルフィン」「ドーパミン」の働き
- エンドルフィン:痛みやストレスを和らげ、気分を高めるホルモン
- ドーパミン:報酬や達成によって分泌され、やる気や快感に影響
これらのホルモンは一見ポジティブな働きをしますが、慢性的なストレス環境下では「脳内麻薬依存」に近い状態になる危険性があります。
深夜残業とメンタル不調の見えないリスク
「頑張っているつもりが、気づいたら燃え尽きていた」
それは、ストレス反応の麻痺と脳の報酬回路の誤作動が起きていたサインかもしれません。
残業を繰り返す中で、無理を重ね、メンタルや身体のバランスを崩すケースは少なくありません。
自覚しづらいからこそ、職場でのストレスの「見える化」が重要です。
職場でのストレス可視化と対策には研修が効果的
けんこう総研では、ストレスチェックだけで終わらない、行動変容までを含むストレス管理研修を提供しています。
科学的測定 × 実践的な行動改善 を組み合わせたプログラムは、管理職や現場スタッフにも取り入れやすく、
実際に離職防止・メンタル不調の予防に効果があったという声もいただいています。
働き方を見直し、健全な「やる気」を生む環境を
ストレスによって生まれる脳内ホルモンの働きは、人間の自然な防御反応でもあります。
しかし、それに頼りすぎてしまうと、身体や心に深刻な影響を与える可能性があります。
大切なのは、無理なく集中できる働き方と、職場環境の整備です。
ぜひ、あなたの職場でも「ストレスと上手に付き合う研修プログラム」から始めてみませんか?